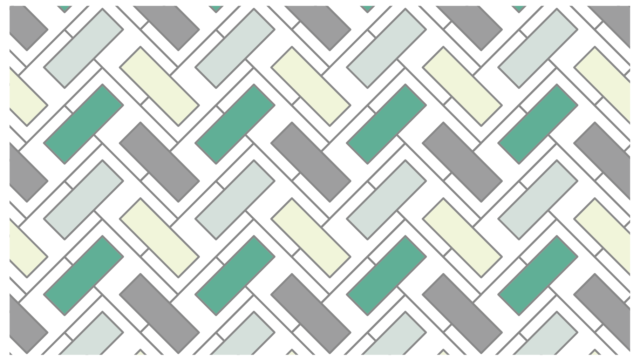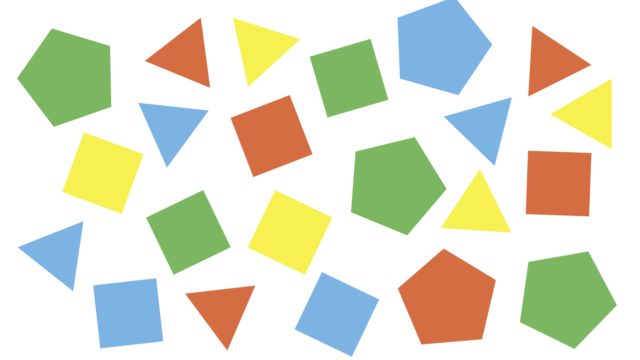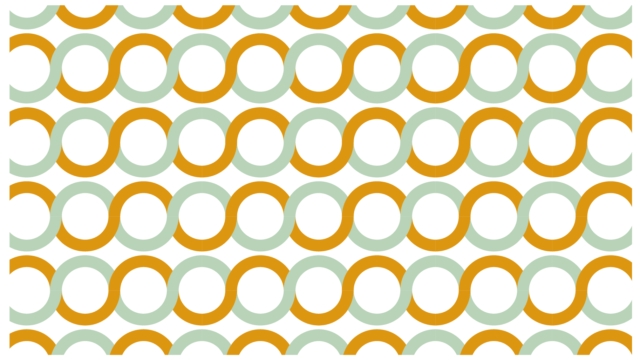映画の中にはさまざまな人生や日常がある。さまざまな人生や日常の中には、整理収納の考え方が息づいている。
劇場公開される映画を、時折、整理収納目線を交えて紹介するシネマレビュー。
もちろん、直接映画に携わっていたわけではなく、それぞれのことが想像の範疇だったといいたいのではない。
作品が発するオーラみたいなものがそう受け止めさせるのだと感じた。
でも「受け止めたい」と思わせる何かがあるのだ。
市子には母・なつみがいる。市子には恋人・長谷川がいる。市子には妹・月子がいる。
市子には母・なつみがいた。恋人・長谷川がいた。妹・月子がいた。
なぜそうなるかといえば、市子が無戸籍の人だからだ。
無戸籍だけど市子はいる。
無戸籍だけど市子はいた。
になるのかは、映画を観た人にはわかるかもしれない。
決して多くはないけれど、市子と関わった人たちが、彼女を語る。
よく、事件が起きた時に報道で近所の人や元同級生が容疑者を語る映像を見る。
「大人しそうだった」「そんなことをするようには見えなかった」「やさしかった」「暗かった」「他人と距離を取っていた」「キレやすかった」
それらを目に耳にする度に、どれも本当のことに思えないと思うことはないだろうか。
特に最近のことではなく、昔のことを語っている証言を聞く度に
そんなフィルターのかかった証言のどこを受け止めればいいのだろうと疑問に思うことはないだろうか。
スクリーンの中では、市子やその周りで起こったことが時を行き来して写し出される。
ひとつひとつの行動や言葉を納得は出来ないけれど、受け止めることが出来た。
少なくとも勝手に一方的に聞かされた印象ではないからなのだろう。
耳を澄ますようなエンドロールが終わり、観客はようやく受け止めていた時間から解放される。
そして想像や印象など曖昧なものを思ったり感じたりすることを許される、そんな気がした。
市子のこと、母・なつみのこと、恋人・長谷川らのことを受け止めた私たちは
日常で、身近にいる誰かのことを受け止めたいと思う。
受け止めていた、ではなく、受け止めている。でありたいと思う。
それは家族関係のことで悩みを抱えている人の話を聞くだったり
新しいことを始める人の決意にうなずくだったり
離れたところに暮らす人に会いに行き手をさするだったり
片付けられないという人に寄り添うだったり