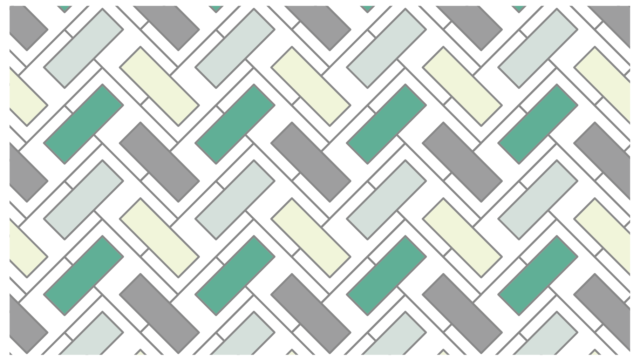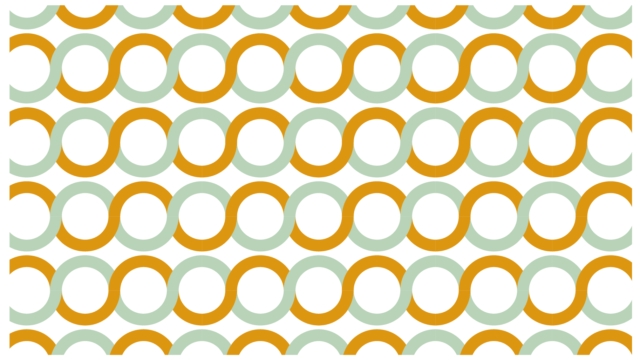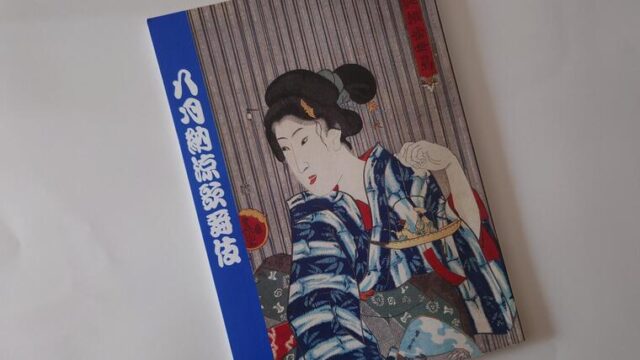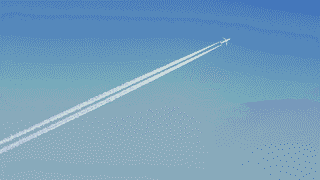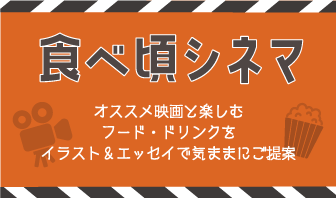歌舞伎をほぼ毎月楽しんでいる60代男性。毎月観るために、座席はいつも三階席。
印象に残った場面や役者さんについて書いています。
「七月大歌舞伎」今月楽しみにしていたのは、昼の部です。七世市川團十郎が構想を立て、九代目が完成させたという「新歌舞伎十八番」から選んだ4演目を上演するからです。
その中でも、印象深いのは、やはり当代市川團十郎の出演する「船弁慶」と「紅葉狩」です。
「二、船弁慶」
前半では源頼朝に追われる源義経(中村虎之介)が、静御前(市川團十郎)を京に帰るよう説得する場面です。珍しく女形を演じる市川團十郎さん。衣装も研究し、顔の化粧も能面のようです。そもそも荒事が得意の團十郎さんが女形を演じるだけで面白かったです。
静御前が、京に帰るよう告げられたのは、義経本人からでなく、弁慶(市川右團次)からでした。しかし別れたくない静御前は、義経本人と話したいといじらしい様子を見せます。
義経本人から、落人の身で女人を連れて旅するのは世間に対し憚りがあると諭されます。盃をかわし、弁慶の勧めで歌詞に都の名所の四季の移ろいを詠みこんだ舞を舞い始めます。
三味線や鳴り物の音楽にのり、女形姿の團十郎さんが舞っているのが珍しく、見入ってしまいました。(小鼓は、田中傳左衛門さんです!)
「別れの言葉は本人から聞きたい」「落ち延びる足手まといにはなりたくない」「再会の時まで我慢する」という感情表現を團十郎さんがしているのを、若干似合わないかも? と思いつつ観ていました。(普段なかなか観られないので興味深かったです。)
後半では、船に乗って逃げる義経一行の前に現れる平知盛の霊を演じます。
派手な隈取、大きく長髪の桂をつけ、大太刀をもち、いかにも死者の怨霊らしい、荒々しい様子の、これぞ市川團十郎という姿で登場しました。
知盛の霊が義経一行に襲い掛かり、義経が太刀を持って応戦しますが、なおも船ごと波間に引きずりこむ勢いです。弁慶が、数珠をもって一心不乱に祈り続け、さすがの知盛の霊もたちうちできず、水底で消えていきます。襲い掛かるところは、力強く、弁慶が祈り始めると、とても苦しい様子に芝居の強弱の差があり、荒事得意の團十郎さんの面目躍如たるものが垣間見られたと感じ、とても楽しかったです。
「四、紅葉狩」
この演目をはじめてみたのは、舞台ではなくてDVDでした。当代市川團十郎さんが市川海老蔵を襲名し、御父上が市川團十郎を襲名した際のパリ公演を収録したものでした。
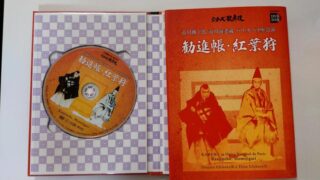
船弁慶とも共通しているのは、團十郎さんが女形を演じること。紅葉狩では、戸隠山の鬼女という化け物を、派手な衣装で演じることです。違うのは、松本幸四郎さんという座頭級の役者の方とお芝居することです。看板俳優が舞台上で火花を散らす様は、素人ながらにとても心が沸き立つ思いがします。團十郎さんは五月の團菊祭以外では、自分の一座だけで興行することも多いので、今回とても楽しみにしていました。
幸四郎さん演じる平維茂が、紅葉狩を楽しむ一行に戸隠山の山中で出会い、主人の更科姫に誘われて酒宴となります。酒宴ですので、音楽に合わせ、皆が舞い始めます。
今回、特に、團十郎さんのご息女、市川ぼたんさんが出演し、舞いを舞います。お顔も可愛く、会場も沸きます。更科姫もやがて舞いはじめ、中村雀右衛門さん演じる局 田毎との連れ舞いや、二枚扇を持った舞いなど、女形で舞う團十郎さんを観る機会はあまりないので、とても珍しく、楽しく感じました。
平維茂が寝入ってしまうと、更科姫が鬼女の本性を見せますが、その時の表情は、眼光鋭い、鬼のものでした。表情を激しく変えられるのは團十郎さんならではですね。
歌舞伎役者さんの中でもずば抜けていると思います。
後半は、鬼女と平維茂との立ち廻りになりますが、荒々しく襲い掛かる姿、名刀の威徳に負け、苦しむ様子などすべてが化け物らしく、面白くてたまりません。
歌舞伎ならではの小道具がキーポイントになるパターンで、名刀小烏丸の威徳に負け、松に飛び移ります。
松の上にいる團十郎さんと、舞台上の幸四郎さんとの引っ張りの見栄で終わります。
看板役者お二人の見栄で終わるところが最高でした。
團十郎さんが、これからも、他の看板役者の方とも共演していただいて、いろんな演目を楽しく拝見したいなぁと感じて帰路につきました。
その他の歌舞伎レポートは、エンタメターミナルの記事
「歌舞伎座「七月大歌舞伎」観劇レポート」をご覧ください。