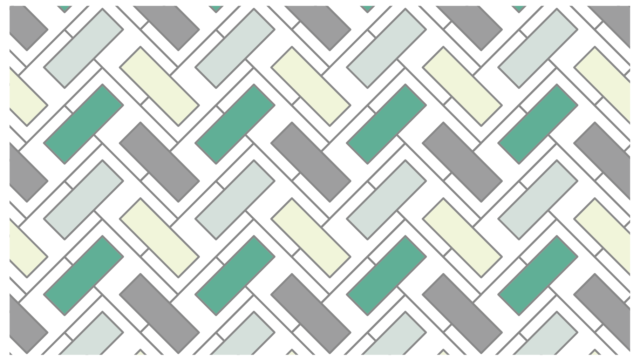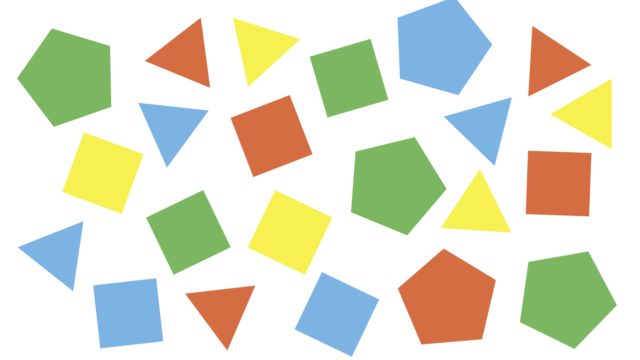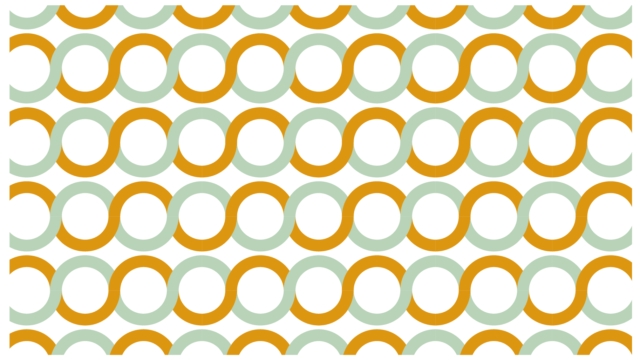日常の中から、エンタメを整理収納目線、暮らしをエンタメ目線でつづります。栗原のエッセイ、つまりクリッセイ。
何十年ぶり過ぎてほぼ初、みたいな状況で広島に行ってきたのは昨秋のこと。
宮島の大聖院で行われた火渡り神事に遭遇した話の前編につづき、後編をお届け。

そうしていよいよ中央にある炉壇と言われるところに火が点火された。
たちまちパチパチ、あっという間にもくもくと煙が立ち、まもなく火柱があがっていく。
その周りを山伏の成りをした修験者たちが囲み、願いが書かれた護摩札を投げ入れていくのだ。
投げ入れる前に、ひと札ひと札確認するようにしている人もいれば、ぐっとひとまとめにしてザバッと投げ入れる人もいて、もうここはあんまり細かいことはいうまい……なのだろう。周りでは信者の方が合わせてお経を唱えている。
諳んじている方も、経本を見ながらの方もいて、このタイミングで裸足になり準備をしている方もいて、大聖院が長くこの地にあり、多くの人の拠り所になっていることもわかった。
この炉壇の火が燃え尽きたら、この上を渡る。これが火渡り神事。
信者の次に一般の人も渡れるようだ。
結論から言えば、私もCさんも、火渡りはしなかった。だってついさっきまで何が行われるかよくわかっていなかったし、護摩札に願いを書いて納めてもいない。
「せっかくだから」が大好きな言葉な私だけど、ここではそれは発揮しなかった。
いざとなると願いが浮かばないというお気楽びとであることもその理由だ。
儀式が終わって、信者、一般の方の火渡りが始まったらここを出ようと考えていた。
たぶんCさんも。
しかし、それが始まる少し前、まだ炉壇が燃えている只中に、マイクを通じてこんな声が聞こえた。
「それではこれからおかじをいたします」
おかじ?
無知を晒すがまたまた初めて聞いた言葉だった。正しくは「お加持」。仏の加護を祈ること、祈祷のことを言うそうだ。
聞けば、火渡りをしなくとも、ご祈祷をしてもらえるという。
手持ちのバッグの中に身分証を入れた状態で、バッグごと修験者たちに渡すと、それを火に近づけてくれて祈祷してもらえるそうなのだ。
これにはCさんと顔を見合わせて、「お願いしたいよね!」と「せっかくだから」モードが点灯した。
3列目くらいにいた私たちは、前の人たちの動きに習い、タイミングを待つ。
先ほど護摩札を投げ入れていたたくさんの修験者たちが、一度に3つ4つのバッグを受け取り、それを火のそばに近づけ、持ち主へ手渡す。これを繰り返した。
少しして、私もCさんもバッグを預けることができ、お加持をしていただき手元に戻していただいた。その間、約20秒くらいだろうか。

その日は、どこに行ってもたいてい褒めてもらえるお気に入りのバッグを持参していたので、そのバッグでお加持をしていただけたのがなんだかとてもうれしかった。
そうして、春は4月15日、秋は11月15日の年に二度しかない大聖院の火渡り神事の見物、なんなら参加ということにしちゃおうか! を終えて、火渡り神事を待つ長い列の横を抜けてその場を離れた。
ちなみに火渡りをした方は足を洗わずに帰宅するようアナウンスがされていた。
参加された方々にご利益がありますように……。
時刻は14時近くになり、お腹もぺっこぺこ。
滝小路を下り、柳小路とぶつかる角にある「岩村もみじ屋」の前にたどり着いた。
ここは前日、宮島でもみじまんじゅうを食べるなら……とKさんが教えてくださっていたお店。焼きたてを店頭で1個から購入できるらしい。
もみじまんじゅうのお土産もここにしようと決めていた。
明治末期創業のこの「岩村もみじ屋」さんは、こしあん、つぶあんのこの2種類だけ。

あっという間に行列できる。(たぶんこの日は空いているほうかと……)

たまらずその場で私だけいただきまーす。あたたかくて、シンプルで美味!
お土産の詰め合わせはこんな感じ。
聞かれていないけど、私は圧倒的つぶ餡派!!

それから先は干潮の鳥居を見に足元まで行ったり、牡蠣づくしの定食をいただいて大満足。
表参道商店街をぷらぷらと往復し、お土産をああだこうだと選ぶのもまた楽し。

旅先ってこういうこともやっちゃうよね。いくつになっても。
 そうして最後は珈琲をいただきながら、戻りの時間をチェックしたり、旅を振り返ってしばしまったり。
そうして最後は珈琲をいただきながら、戻りの時間をチェックしたり、旅を振り返ってしばしまったり。

実はCさんとは帰りの飛行機の空港が別だったので、荷物を預けていたJR宮島口駅で別れることになっていた。
「ああ、楽しい旅が終わっちゃうね」
「それにしても最高だった。これ、書きますから……」と
いーっぱいの楽しさとネタを手に入れたことでご機嫌のラストカフェオレだった。
と、宣言しながら記事を書き終えたのは、秋の安芸旅からちょうど2カ月。
冬の宮島はどんな感じなのだろう?
つくづく尽くした2泊3日。
たくさんアドバイスくださったKさん。
そして旅を楽しくご一緒してくださったCさんに感謝を込めて。
(終わり)
写真/Akiko Kurihara、Chikako Matsuura