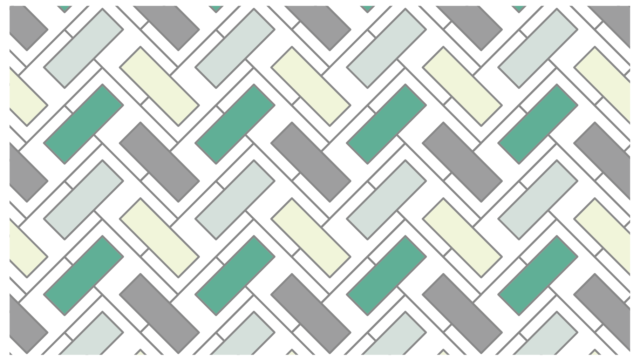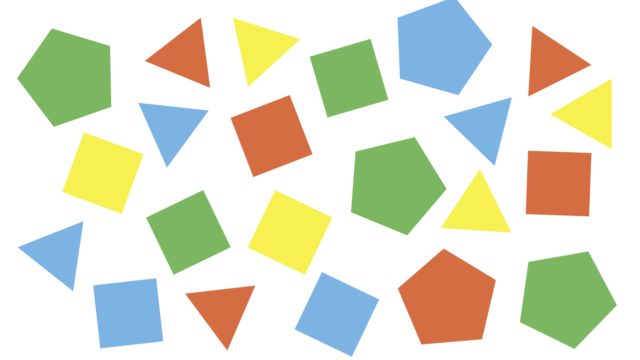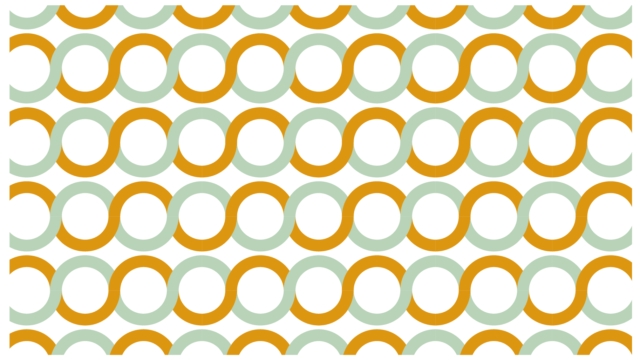映画の中にはさまざまな人生や日常がある。さまざまな人生や日常の中には、整理収納の考え方が息づいている。
劇場公開される映画を、整理収納目線を交えて紹介するシネマレビュー。
「旅立ちの前、僕は人生を整理する--」
これは、この映画のキャッチコピーとしてチラシやポスターに書かれた言葉だ。
そして、この映画の中には「人生のデスクの整理」というワードが出てくる。
これは末期がんの男が最期を迎えるまでの物語。
そう書いてしまえば、なんとなくこれまで観てきたさまざまな作品を思い浮かべ、
そうした作品は避けたいと思ったり、避けてきた人も多いのではないだろうか。
でもこれは、人生のデスクの整理とは、一人で行うもので、でもそれには誰かの力が必要ということを知らせてくれる物語だ。
俳優で今は若者に演技を教えているバンジャマン(ブノワ・マジメル)は、ステージ4の膵臓がんに侵されていた。生きるために名医といわれるドクター・エデ(ガブリエル・サラ)の元を訪ねるバンジャマン。傍らには、彼の母、クリスタル(カトリーヌ・ドヌーヴ)が息子をなんとか助けたいと悲痛な面持ちでいる。
ドクター・エデが告げたのは、病状に関するありのままの報告と、いつかがんに負ける日が来るという真実。そして、生活の質を維持するための化学療法のすすめだった。
自暴自棄になるバンジャマン、何も出来ず取り乱し、自分を責める母。
ドクター・エデは、そんな二人に穏やかに向き合う。

バンジャマンは孤独な40代の男だ。なぜこの俺が? という言いようのない不安と不満を、時に母にぶつける。それは性別や年代が近かろうが、遠かろうが想像できる反応だ。
そうなりながら、演劇を志す俳優の卵たちに、情熱を込めて演技指導を行う。
ワークショップで演じる彼らのリアルが、緊迫感のあるカメラワークによって伝わってくる。自己を解放せよ、感情をむき出しにせよと若者たちを力いっぱい煽るバンジャマンから出る、哀しみとエネルギーに心拍数が上がる。

ドクター・エデは、患者に寄り添うだけでなく、医療に従事する看護師やケースワーカー、音楽療法士らにも寄り添う。死と向き合う仕事をする者同士が、素直に感情を吐露したり、存在を感じ合うことを大切にしている場は、とてもリアルでとても重要だ。
それらはドキュメンタリー映画のようなシーンに映るが、それもそのはずで、ドクター・エデを演じるガブリエル・サラは実際も医師なのだ。
ドクターはあらゆる場面で患者を、仲間をファシリテイトする。

そして気になる「人生のデスクの整理」というワード。
これは、死を前にして、自分の人生で心残りとしてあることを見つめ、片付けることを意味している。
バンジャマンの場合は、昔愛した人との間に認知していない息子がいることだった。
末期がんだからと言ってすぐにすべてが赦されたり、納得できるものではない。
それは、心残りがいかなる内容のものであってもそうだろう。
まずは全部出す、事実を見つめることからだ。
そして、どうすべきかではなく、どうしたいかに向き合う。
どうしたいかが見えてきたら、そのための一歩を踏み出す。
モノの整理とも、思いの整理ともリンクする。
人生が続く場合は、その先何度でも振り返り、見直しを図ることができる。
では、人生が終わる場合はどうか。
ここで人生のデスクの整理をしておけば、そこに関わった人たちそれぞの人生で、何度でも振り返り、見直しを図ることができるということだ。
大切な人を亡くした経験がある人や、自身が病を患ったり、現在患っている人には、もっとリアルで、それぞれ違う思いに至るだろう。
記憶や老化という壁が立ちはだかり、「人生のデスクの整理」が容易にはいかない人だって当然ある。
でも、この映画を観たら思える。
「人生のデスクの整理」がきっといつかは必要になるということを。
タイトルの「愛する人に伝える言葉」とは、死を前にするバンジャマンにドクター・エデが伝えた5つの言葉のことだ。
「俺を赦して。俺は赦す。ありがとう。さようなら。愛してる」
もしかしたら、この言葉は、人によって違うのかもしれない。
「人生のデスクの整理」をするときっとその言葉が鮮明になるのだろう。