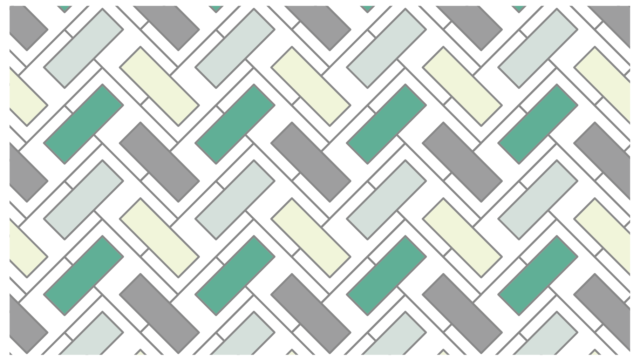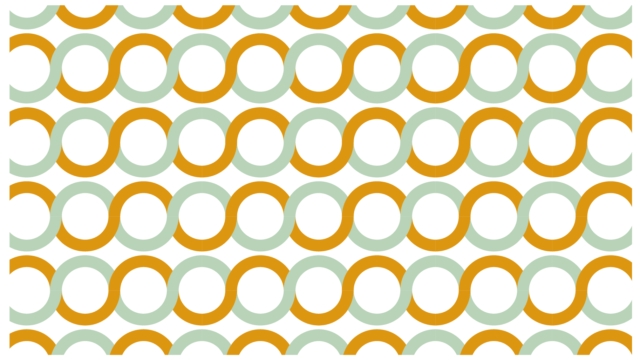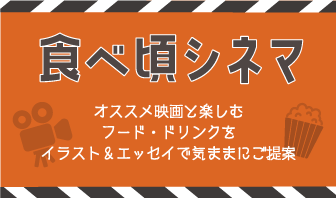歌舞伎をほぼ毎月楽しんでいる50代男性。毎月観るために、座席はいつも三階席。
印象に残った場面や役者さんについて書いています。
今月は、松竹創業130周年を記念した、通し狂言「仮名手本忠臣蔵」です。一つの物語を朝から晩までかけて上演します。
今回は、自分のミスで、チケットが取れていなかったことが1週間前に発覚し、大慌てで空席を探したため、結果的に夜の部だけの観劇となってしまいました。
忠臣蔵は江戸時代のお話ですが、題材になった人物の名前をそのまま使ったりできませんので、時代設定を鎌倉時代にしたり、似せた名前を使ったりしています。また、最後は討ち入りとなりますが、それまでは四十七士に個人的にスポットライトをあててお話が進んでいきます。
配役はAプロ、Bプロの二種類に分かれています。ミュージカルとかにはよくあるダブルキャストです。私が観たのはAプロでした。
夜の部の「五段目 山崎街道鉄砲渡しの場、山崎街道二つ玉の場」と「六段目 与市兵衛内勘平腹切の場」は、早野勘平がメインになります。
本日は尾上菊之助さんが演じておられます。早野勘平は、それまでのお話で主君の塩谷判官が、高師直に殿中で刃傷に及んだ際、恋仲の腰元おかるとの逢瀬を楽しんでいたため、主君の一大事に間に合わず、それを恥じて腹を切ろうとしたところ、おかるに説得されて、京都の山崎へ逃げていきました。その後、塩谷判官の敵討ちに参加したいという思いを抱えながら、狩人に落ちぶれているところから夜の部のお話が始まります。
特に「二つ玉の場」が見ものです。今の時代には信じられないことかもしれませんが、夫が再び侍に戻れるための費用を捻出するのに、妻のおかる(中村時蔵)は祇園の遊郭 一力茶屋に百両で身を売るのです。半分の五十両を受け取った父の与市兵衛が休んでいるところを、斧定九郎(尾上右近)が刺し殺して五十両を奪います。
台詞は「五十両」とだけ言います。今まで女形やきれいな立役の印象が強い尾上右近さんですが、盗みをするために冷酷に人を殺してしまう悪さがしっかり伝わるよう演じていました。短時間の出演でしたが、インパクトは非常に大きかったです。
斧定九郎はその後、早野勘平(尾上菊之助)に銃で撃たれ命を落とします。獲物を仕留めたと思った勘平が近寄ると人でした。「こりゃ人」と一言発します。手当をしようと薬はないか懐に手を入れると、五十両入りの財布に気づき、迷った末、奪って逃げてしまいます。
「六段目 与市兵衛内勘平腹切の場」では、誤解が重なってストーリーが展開されていきます。勘平が殺したのは与市兵衛という誤解、勘平が手にした五十両は与市兵衛から奪ったものだという誤解です。実際、結果としては、おかるが身を売って作ったお金を、斧定九郎から奪い返したことになりますが、義父を殺して得た金で敵討ちに参加できるようとりなしを頼んだと誤解され、敵討ちにも参加を認められず、主君の一大事に参加できない不忠ものであることを恥じて、刀を腹に突き刺します。名誉ある死にざまでないため、「切腹」でなく「腹切り」という表現が歌舞伎ならではです。
また「親を殺してしまったのではないか」「何とか敵討ちに参加したい」という複雑な気持ちでいる勘平を菊之助さんは見事に演じておられました。表情や身振りもいいのですが、声が小さくしゃべっても、大きく響くとでもいうのでしょうか。
音羽屋には、声の良い方がたくさんいらっしゃいます。菊五郎さんもそうですし、彦三郎・亀蔵のご兄弟、松也さんもそうです。次の音羽屋の頭となられるのにふさわしいと感じました。
「七段目 祇園一力茶屋の場」。この演目は、単独で数多く演じられます。設定としては、討ち入りを考えていることを悟られないよう遊び惚けている大星由良之助(片岡愛之助)。討ち入りの考えを表明するまでの場面で、遊女になったおかると、その兄、寺岡平右衛門(坂東巳之助)が絡んできます。
大星由良之助を演じる片岡愛之助さんは、遊び惚けていながらも、心の奥底に主君の仇を取ることを秘めているように感じました。
「十一段目 高家炭部屋本懐の場」は、討ち入りの場面です。立ち廻りのシーンも多く、最後の引揚げの場では、橋の上に四十七士(一人は早野勘平で、腹切りで死んでいるので実際には四十六人)が勢ぞろいしたところに、尾上菊五郎さん演じる服部逸郎が登場し、裏道を通るよう諭します。最後に出てきて持っていくなぁという感じです。
歌舞伎座では長い演目を通しで見せる作品がラインナップに上がることは少ないですから、こうした企画は楽しく感じます。うっかりチケット手配ミスをして、昼の部がみられなかったのがつくづく残念ですが……。
秋にも通し狂言がありますので、その際は、必ず最初から最後まで観劇したいと思います
その他の歌舞伎レポートは、エンタメターミナルの記事