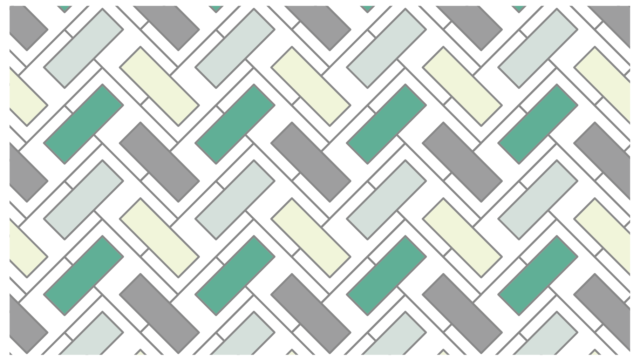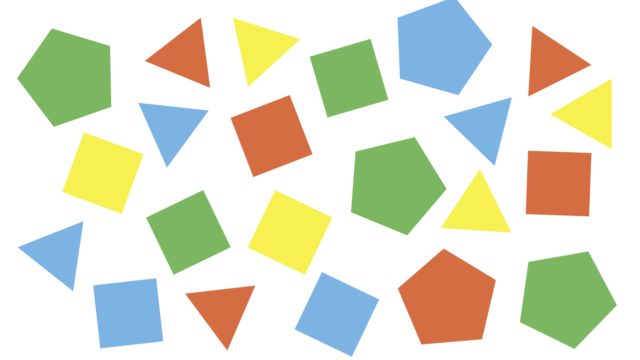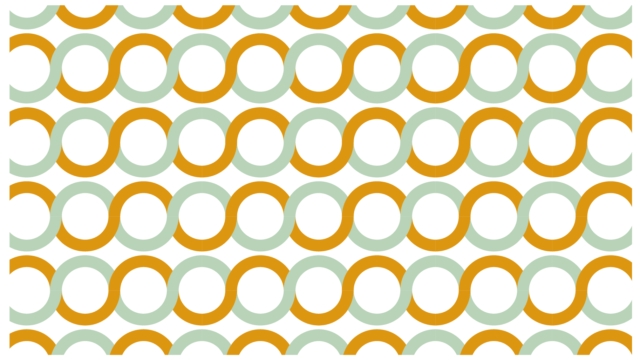ステージには神様がいるらしい。 だったら客席からも呼びかけてみたい。編集&ライターの栗原晶子が、観劇の入口と感激の出口をレビューします。
※レビュー内の役者名、敬称略
※ネタバレ含みます
『リンス・リピート-そして、再び繰り返す-』を紀伊國屋サザンシアターで観た。
観た後に、一緒に観劇した方々と感想や諸々をお話できる贅沢な時間付き。
舞台は一面ピンク色。バックの布は縮緬のようなシワが加工されている。私は和紙みたいだなーと思いながらそれを観ていた。
ピンクの背景にポツンと置かれたピンクの冷蔵庫。そして照明が一つ吊り下がっている。ネオン管がグニャリとしたようなユニークな形は、オシャレな北欧インテリア照明みたいだ。花のようにも見えるし、頭の中のモヤモヤみたいにも見える。
そうしてレイチェルを中心にしたテルナー一家の物語が始まった。
少し背を丸め、ダボッとした服に着られているようなレイチェル(吉柳咲良)は、摂食障害の治療のために入所していた施設から、一時帰宅してきた。
腫れ物に触るようなぎこちなさ。ギシギシ、ガザガザと軋む音がするようだ。
縮緬のようなと言っていたピンクの布が、サメ肌とかおろし金のように見えてきてしまう。
その相手は母・ジョーン(寺島しのぶ)。帰宅した娘に「私もハグしていい?」と確認することのぎこちなさと、した時のぎこちなさ、いきなり観ているこちらにも力が入った。
父・ピーター(松尾貴史)は、施設にも面会に度々訪れているため、レイチェルとの距離感が近いつもりでいる。私はレイチェルの理解者だと妻に対して優位に立つような言動があきらかに娘を困らせていることに気づけていない。
レイチェルは「大丈夫」を繰り返す。大丈夫を言えばいうほど、大丈夫なんかじゃないってことは、たとえ同じようなつらい経験をしていない者でも想像がつく。
そう思いながら、もう物語のかなり始まりの段階で私は、この舞台を同じようなつらい経験をした方が観たらどうなるのだろうか……そのことをぐるぐると、ぐるぐるぐると考えながら観ていた。
レイチェルには弟・ブロディ(富本惣昭)がいる。弟とは肩の力が少し抜けたような感じで会話ができるようだ。でもそのブロディは父とはなんだか折り合いが悪い。反抗期という感じだろうか。いや、なんかもっと根本的に理解し合えないムーブがある。
ギシギシ、ガザガザはつづく。
あー、しんどいよーと思うタイミングで場面は暗くなり、薄暗い中をピンクの上下(つなぎ?)に身を包んだ黒子ならぬ桃子が数名出てきて、テーブルの上やキッチン台の上、ベッド代わりのクッションのそばを片付けて、次の準備をする。
引越し屋さんの作業みたいに見えたけれど、「いざ新生活へ!」みたいな希望感はないから、冷静に淡々と進めている感じが、レイチェルを取り巻く環境にリンクしていた。
腫れ物に触るような……になる一番の理由は、レイチェルの摂食障害だ。施設で治療のために習慣化している食事条件を満たすためには、家族がしっかり見て、家族とともに食事の時間を取るのが必須条件だった。
しかし、それは残念ながら叶えられない。
そこから一家の関係性、抱えているもの、抱えきれていないものが表面化していく。
登場人物がもう一人いる。施設のセラピスト・ブレンダ(名越志保)だ。レイチェルには、毅然とした姿勢でファシリテイトしているようだ。面会に訪れないジョーンに対しては何か思いがありそう。
こうして書き出していくと、ただただ緊迫した場面が続くように感じるが、実際に目の前では家族がたくさん言葉を口に出していた。決して噛み合ってはいないのだが、言葉を発していることが、なにか救いに感じたのは、私が沈黙が苦手なタイプだからだろうか。
ジョーンが抱える問題は、彼女の言動で見えてきたし、
ピーターがコントロールできていない問題は、彼のふるまいで見えてきた。
ブロディが姉に発する言葉には、姉弟が背負っているものを想像させたし、
なによりレイチェルが発しているサインは、家族以外にはしっかり見えている。
感情の全部出しは、舞台の上でなされていくのだ。
でも、簡単には片づかない。全部出したつもりでもまだ隠れているものがあるから。
簡単には整わない。
無理に箱に詰め込んでも、それはすぐにまた乱れるのだ。
整理収納と同じだよ。
ミュージカル俳優として活躍めざましい吉柳咲良さんの、これが初のストレートプレイ。
よーく聞こえるように声を張ったりしない、母を拒絶し、母を求めて、母を恐れているけれど、愛をわかりやすく欲する悲劇のヒロインになっていないのがとてもリアルだった。
寺島しのぶさんのジョーンは無敵に見えて、一番抱えている闇が大きいことが物語が進むにつれて色濃くなっていくのだが、その不協和音がクレッシェンドしていく感じが、しんどいの倍々ゲームだった。特に松尾貴史さんとの夫婦の会話は息が合わなすぎるキャッチボールだ。投げたら投げ返すルールは無視し、互いのボールを食い気味に投げ合ったり逸らしたりする。いや、もう子どもにとってはこんなのしんどすぎるって。
だからこの二人の関係を受けて、富本惣昭さん演じるブロディは、距離を取ることで調整を試みている感じに見えたのかもしれない。ブロディは養子だから、出方を間違えれば自分の居場所を失うかもしれない、そんな何かがどこかにくすぶっているのかもしれない。
そして名越志保さん演じるブレンダ。とにかくその声のトーンには、感情を混ぜることで台無しにしないようにするセラピストとしての慎重さと使命感が宿っていた。そこに人間愛もチラ見せしていた気がする。
低い低い弦楽器の音が幾度となく流れた。登場人物たちの心と体と頭の中に流れる鈍痛を帯びた音にも聞こえたし、心を保とうとする人間の踏ん張りのようにも私は聞いた。
レイチェルは、一時帰宅の時間を経て、自ら決断をしたところで物語が終わる。
この先、彼女は体を治した後、母と距離を取るのかもしれない。
たまに会う時は、ぎこちなさがしばらく残るのかもしれない。
でも家族の形を見つけて、続いていくのだ。そうであれ。願って、祈るような気持ちで舞台を見届けた。
さて、冒頭に触れた舞台は一面ピンク色。バックの布は縮緬のようなシワが加工されているのは、子宮をイメージしているのだそう。
一緒に観劇させていただいた方の中に、それに気づいた方がいた。
そうか、なるほど、そうなんだ……公演パンフレットの美術・衣裳解説のページにも書かれていた。
そしてやっぱり私は帰り道でも考えていた。
母と娘、ちょっといろいろあったあの友人・あの知人がこの舞台を観たら、どんな感想を抱くのだろう。苦しくなったりするのだろうか。
『リンス・リピート』の脚本を書いたドミニカ・フェローさんはご自身の摂食障害の経験も踏まえてこの作品を書き上げたのだという。
2025年4月17日(木)~5月6日(火)
紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
2025年5月10日(土)~5月11日(日)
京都劇場
出演/寺島しのぶ、吉柳咲良、富本惣昭、名越志保、松尾貴史
脚本/ドミニカ・フェロー
翻訳/浦辺千鶴
演出/稲葉賀恵
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。